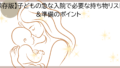こんにちは、ぬいcocoです。5人兄弟を育てている母ちゃんです。
「うちの子にお小遣いをどう渡せばいいの?」と悩むママやパパは多いですよね。うちもお小遣いについてずっと悩んできました。なんなら、今でも試行錯誤の毎日です。
お小遣いは、子どもにお金の使い方を学ばせる大切な機会。でも、渡し方や金額、ルールは家庭によってさまざまです。
そこで今回は、わが家のお小遣い事情を公開しながら、お小遣いの渡し方や管理法について徹底解説!お金の使い方を上手に学べる仕組みづくりのヒントをお届けします。
1. うちのお小遣いルール

わが家では、お小遣いを「お手伝い制」にしています。また、お小遣い帳をつけることで、自分のお金の使い方を管理できるようにしています。
✅ わが家のお手伝いのルール
- 家の手伝いをすればするほどお小遣いが増える仕組み。
- 例:お風呂掃除 20円、下の子の面倒を見る 30円 など
- 勉強や学校、習い事での成果も加算対象。
- 例:テストで100点を取ったら100円、運動会で1位を取ったら100円 など
この方法を取り入れることで、「計画的に使う力」と「お金を得るための努力」をバランスよく学べます。
また、お小遣い帳をつけることで、「何に使ったのか」を見える化。これにより、 「このお菓子、こんなに高かったんだ!」「もっと貯めて別のものを買えばよかったかも」と、物の価値を考える力が育ちます。
お金はただ与えるだけではなく、稼ぐ経験と管理する習慣をつけることで、その大切さが身につくもの。わが家のルールが、少しでも参考になれば嬉しいです!
2. みんなのお小遣い事情ってどうなの?
調査によると、小学生のお小遣いの渡し方や金額には学年による違いがあるようです。
✅ 低学年(1-2年生)
- 月1回の定期的なお小遣い:中央値500円、平均1,004円
- ときどき渡す場合:中央値163円、最頻値100円
- 使い道:お菓子、ジュース、おもちゃ、ゲーム、文房具、本、マンガ、家族へのプレゼントなど
- 渡し方の傾向:「ときどき」が約6割、「月1回」が1割強
✅ 中学年(3-4年生)
- 月1回の定期的なお小遣い:平均864円
- ときどき渡す場合:平均923円
- 使い道:低学年と同様だが、ゲームソフトや交通費にも使用
- 渡し方の傾向:「ときどき」が5割、「月1回」が3割程度
✅ 高学年(5-6年生)
- 月1回の定期的なお小遣いが増え、金額も上がる傾向
- 使い道:マンガ、本、雑誌の購入が増加。友達との外食や遊びにも使用
- 渡し方の傾向:「月1回」が約5割近く
学年が上がるにつれて、お小遣いの渡し方も「ときどき」から「月1回の定期支給」へと移行し、お金の使い方も変化していきます。
3. お小遣いの使い道とルール
子どもたちはお小遣いをどんなことに使っているのでしょうか?
- 低学年:お菓子、文房具、小さなおもちゃ
- 中学年:ゲームソフト、交通費、マンガ
- 高学年:マンガ、本、友達との外食や遊び
わが家の低学年と中学年の男の子たちも、お菓子やカードゲーム、ゲームの課金など、その時代に合ったお金の使い方をしています。 最近では、スマホゲームやNintendo Switchのオンライン課金が欲しいと言われることも増えてきました。
親としては「課金はもったいないのでは?」と感じることもありますが、 子どもたちと話し合いながら、価値を考えた上で使うルールを決めています。
4. わが家のお小遣い失敗例と改善策
実は、わが家では少し前まで「定額制」を採用していました。毎月決まった額を渡していたのですが、これだと家のお手伝いをしなくてもお金が入ってくるため、子どもたちが「お金の大切さ」をあまり意識しなくなってしまいました。
そこで、お金の管理を学ばせるために 3つのルール を作ることにしました。
✅ お小遣い帳をつける → 何に使ったか記録する習慣をつける。
✅ 「貯める・使う・分ける」 → 例:半分は貯金、半分は自由に使う。
✅ 使いすぎたときの話し合い → 無駄遣いしたら次回の対策を考える。
このルールを続けることで、「使いすぎた!」と後悔することが減り、計画的にお金を使えるようになってきました。
まとめ
お小遣い制度は、子どもの金銭感覚を育てる大切な仕組みです。ルールを決める際は、家庭の方針に合わせながら、子どもが主体的に考え、学べるよう工夫するとよいでしょう。
また、お小遣いの使い方について親子で話し合う時間を設けることで、お金の価値や計画的な使い方を学ぶきっかけになります。貯金の習慣をつけたり、買い物の優先順位を考えたりする経験は、将来の経済的な自立にもつながります。
お小遣いを単なる「お金を渡す仕組み」にするのではなく、子どもが成長しながらお金と上手に付き合えるようサポートしていきましょう。
お小遣いは、ただのお金ではなく「お金の使い方を学ぶための道具」。
みなさんの家庭でも、お子さんに合ったルールを作って、お小遣いを楽しく管理してみてくださいね!